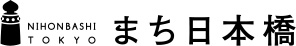- ホーム >
- 「日本橋ごよみ」のご紹介 >
- 日本橋で○○しました >
- 職人さんのお仕事拝見
受け継ぎたい日本の伝統工芸品 職人さんのお仕事拝見
今月号の「日本橋で○○しました」は、拡大バージョンでお届け。異業種の人々が集まり、日本橋でさまざまな社会奉仕活動や環境保全活動などを行う「東京日本橋ロータリークラブ」。同クラブが江戸伝統文化の技術を支援するために主催した「日本橋伝統文化芸術振興プロジェクト」で、江戸伝統文化の技術を継承する3名の方々が表彰された。今回は、その方々の職場を訪れ、技術を継承するために心がけていることや仕事のやりがいについてお話をうかがった。
うぶけや
まずは、天明3年(1783年)創業の打刃物の老舗 うぶけやへ。包丁、鋏はさみ、毛抜きなどの製造、販売のほか、修理、加工も行う。八代当主の矢﨑豊さんは、加工と修理を行いながら店頭にも立つ“職商人”として、日々お客様に向き合う。「包丁一つをとっても板前さんの場合は薄めに研ぐなど、研ぎ方のリクエストが人によって違います。直接話を聞き、できるかぎりお客様の要望に応えられるようにしています」と、矢﨑さん。かつては下した職しょくがいたので、研磨の荒仕事をやってもらえたが、現在は矢﨑さんとご子息の大貴(たいき)さんの二人だけで、最初から最後の仕上げまでを行っているという。ミリ単位の細かい仕事だが、同じことを毎日コツコツ続けていくことが大切だそう。
江戸屋
次に訪れたのは、享保3年(1718年)創業の刷毛ブラシの老舗 江戸屋。糊を塗るための経師刷毛や化粧用の白粉刷毛、織物に使う染色刷毛などは“江戸刷毛”という東京都知事指定の伝統工芸品になっている。代表の濱田捷かつ利としさんは各地に約100人いるという職人の養成に力を入れている。「刷毛は、さまざまな長さの毛を混ぜることでコシを出しています。ブラシの中には、職人が毛を手植えしてつくるものもあります。日々の暮らしの中で、“本当にいいもの”をぜひ使っていただきたいです」と、濱田さん。歯ブラシ、靴ブラシ、掃除用ブラシなど、店内の商品を実際に手に取ると、職人の丁寧な仕事ぶりが伝わってくる。
岩井つづら店
3軒目に訪れたのは、明治初期創業の岩井つづら店。明治から大正にかけて、呉服店が栄えた日本橋にはつづら店もたくさんあったが、現在この地域に専門店として残っているのはこの店のみ。四代当主の岩井良一さんが手がけるのは、専門の職人が編んだ竹かごに和紙を貼り、柿渋で下塗りしたあとにカシュー漆を塗り、内側に化粧紙を貼って仕上げるまでの一連の作業だ。「いちばん人気は、幅33cmの手文庫です。A4サイズのクリアファイルが収納できるので、書類ケースとして使えるんですよ」と、岩井さん。
20個ほどを仕上げるのに約5日間かかるというつづら。軽くて丈夫なうえに通気性がよく、防虫効果もあることから、着物や衣類だけでなく、書類や小物の収納にもぴったりだ。竹かごを編む職人はだんだん減っているものの、つづらを仕上げる職人は育っているという。
うぶけや
東京都中央区日本橋人形町3-9-2
☎03-3661-4851
9:00~18:00(土曜~17:00)
日曜・祝日休
www.ubukeya.com
江戸屋
東京都中央区日本橋大伝馬町2-16
☎03-3664-5671
9:00~17:00
土・日曜・祝日休
www.nihonbashi-edoya.co.jp
岩井つづら店
東京都中央区日本橋人形町2-10-1
☎03-3668-6058
9:00~18:00
日曜・祝日休
https://www.tsudura.com